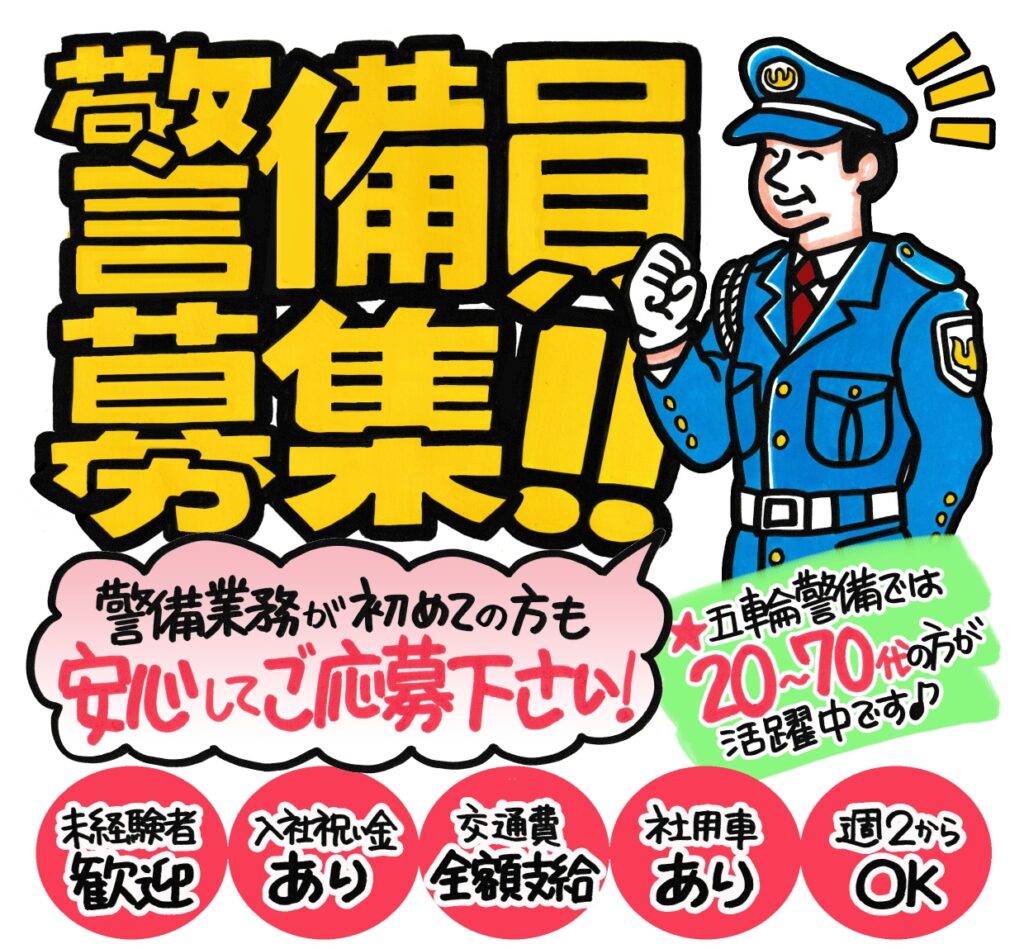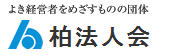護身用具。
大体の警備会社には常備している物だと思います。
ただ、当社ではほとんど使用しません。
何故なら危ないから。
そして、会社に設置する際も、使用の際も、警察への届出が必要になり
余程危険な作業に従事する隊員じゃない限りは許可が下りません。
保管方法も規定されております。
そんなめんどくさい護身用具ですが、持っていない会社というのは、あまり無いのではないかと思います。
見たこともないよーって警備員さんもいるかもしれません。
見たことないものであっても、警備を行う者にとって、種類と使い方くらいは知っておかないと
ちょっと恥ずかしい物でもあります。
今日はそんなお話です。
結論から言うとほとんど使わない
まず最初に、こういう武器があるから(使え)カッコいいから警備員になりたいという人も
少なからずいるかもしれませんので、これだけは言えます。
ぶっちゃけほとんど使えませんし、飾ってあったりすることもありません。
(危ないからね)
警備会社は護身用具を厳重に保管、管理する義務がありますので
研修時に少し見ることはあるかもしれませんが
余程の事がない限り業務で使用することも
触ることもないと思ってくれればいいと思います。
ただ、練習用の柔らかい素材で作られた護身用具というのもあるので、それは使うことはあるかと思います。
護身用具と一言で言っても種類がある
護身用具と一言で言っても、沢山の種類があります。
まずはその種類をご紹介します。
警戒棒

お巡りさんが良く持っているアレですね。
昔は「長さ60センチメートル以下で直径3センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒」と規定がありましたが
警備業法の改正によって、その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え 90センチメートル以下でなければいけません。
また、重さについても細かく規定があり、下記の重さでないといけないこととなっております。
| 30cmを超え40cm以下 | 160g以下 |
|---|---|
| 40cmを超え50cm以下 | 220g以下 |
| 50cmを超え60cm以下 | 280g以下 |
| 60cmを超え70cm以下 | 340g以下 |
| 70cmを超え80cm以下 | 400g以下 |
| 80cmを超え90cm以下 | 460g以下 |
古い警戒棒って重いんですよね・・・
なので、当社では古い警戒棒は研修用としての保管を行っております(それならOKらしいです)
また、警戒棒は使用の場所が限られており、部隊を編成するような現場では使用できません。(競輪場などの公営競技上では使用可)
警戒杖

なーんてことない、単なる棒きれに見えますが、警戒杖と言います
たまーに警察署の前でこれを持って立哨している警察官の方がおられます。
これは私は資格取得の際に何回か使ったことがあります。
叩かれると結構痛いです。
この警戒杖も長さと重さに規定があり、下記の長さ、重さの仕様でないと所持は不可となります。
| 90cmを超え100cm以下 | 510g以下 |
|---|---|
| 100cmを超え110cm以下 | 570g以下 |
| 110cmを超え120cm以下 | 630g以下 |
| 120cmを超え130cm以下 | 690g以下 |
警戒杖も警戒棒と同様に使用する場所が限られており
部隊を編成するような業務には使用できないのは勿論、
警戒杖は使用可能な現場が以下のような場所に限られます。
- 機械警備業務(指令業務は除く)
- 空港
- 原子力発電所、その他の原子力関係施設
- 大使館、領事館、その他の外交関係施設
- 国会関係施設、政府関係施設
- 石油備蓄基地、火力発電所等電直関係施設、鉄道、航空関係施設等テロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
- 火薬、毒薬、劇物を取り扱うような施設で、同様にテロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
- 核燃料物質運搬警備業務と貴重品運搬警備業務
- 競輪場などの公営競技上では使用可
刺又

サスマタと呼びます。
不審者に対して近くに寄らせないようにするものです。
サスマタは会社に保管してあるそうですが、見たことも使用したこともありません。
ただ、変な人が入ってきたときに非常に役立つので、各社1本はあるのではないでしょうか。
所持や使用は届出制
これらの護身用具は警備業法17条2項により、あらかじめ都道府県公安委員会に届け出をしたものしか携帯や使用ができません。
また、使用する前日までに規定の様式に従って届け出をする必要があり、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられます(警備業法58条3項)
要は、会社に置いておいていいけど、警察署に届け出てください。
使用する前日までに届け出てください。
ということになっておりますので、勝手に使わないよう、それだけは十分注意していただければと思います。
保管方法も施錠が出来る場所に保管しなければなりません。
気が付いたら警戒棒1本どっか行ってたって話になると、誰が勝手に持ち出しているか分からない状況は
周辺地域の治安に不安を与えることとなりますので、必ず厳重な保管を徹底するようにしましょう。